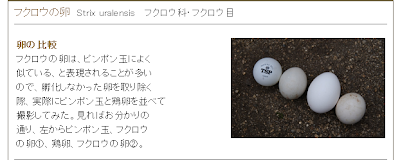秋田には素晴らしい素材があるのに、料理ができないため売り出せないでいる。今日はそのヒントをヒューマンクラブ40周年記念でいただいてきました。
1、ヒューマンクラブ40周年記念
秋田ヒューマンクラブとは、民間の文化団体であり、機関誌「原点」を毎年二回発行しています。
会長の西木正明さんのお話では、今出版の世界は大変であり、こんなに続いているのは奇跡だとお話していました。
(ヒント 1)
地方でいて、会費だけの(広告は至って少ない)会でありながら、リーダーを中心に外に呼びかけていれば会員も増えています。(私も幹事長の武藤さんから、ご丁重なお誘いの手紙で入りました)
2、国際教養大学 中島学長のお話
秋田 国際教養大学の中島嶺雄学長のお話で、二つのことが心に残りました。
信州生まれの学長が秋田と信州を比べて、どちらも県民歌を歌うと県民の胸にジーンと響いてくる。
二つ目は、鹿角市毛馬内生まれの京大の東洋史学者:内藤湖南博士を高校生はもとより、県民が知らない、もっと勉強しよう!!
(ヒント 2)
・秋田県民歌「秀麗無比なる鳥海山よ・・・」は県民を一つとする歌で、宝物である。
・内藤湖南、平田篤胤、佐藤深淵などなど・・・日本のトップレベルの先人がいることを知る。勉強して追いつく、活かす。
3、秋田のエレクトーン奏者 雄鹿賢哉さん
素晴らしい才能のある若き演奏者を見せていただきました。エレクトーンはあらゆることができるのですね。デジタルの一つの方向でしょう。民謡からオーケストラまで・・・いろいろ堪能しました。
(ヒント 3)
・彼の、エレクト~ンで秋田民謡の編曲演奏が、秋田国体やヤートセに使われている。演奏を聴きましたが皆さん感動でした。この方向なら多くの県民に受け入れられますね。
4、本物はまた別次元でした
夜はアトリオンで、渡辺玲子さんのピアノと、布谷史人さんのマリンバ演奏を聴いてきました。
本物の音は、魂を揺さぶる、別次元のものでした。

今日は 私にとっての文化の日でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・