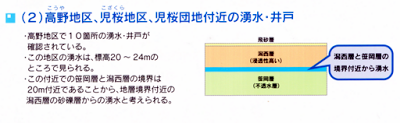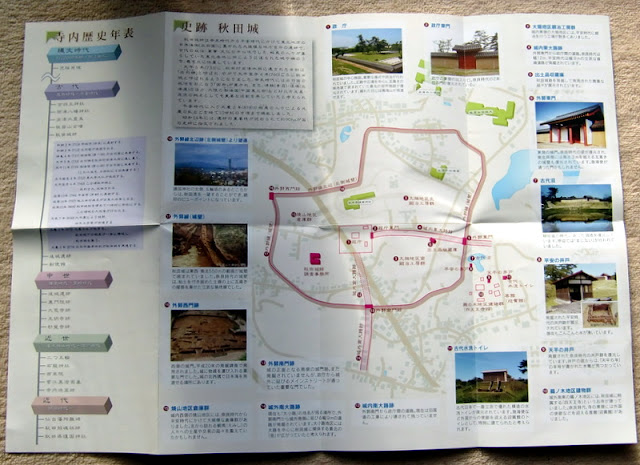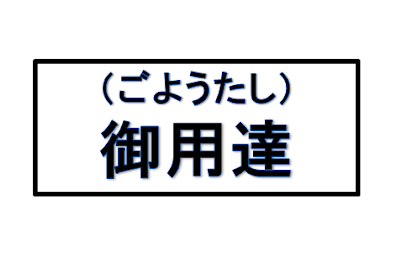常識としての歴史は正しいのでしょうか・・・みんな「ウソ」のようです!!
(とりあえず縄文時代)
1、縄文時代は本当に文化が低かったか
「考古学はまやかし」より
http://ameblo.jp/calseed/entry-11894455636.htmlから
歴史常識的には低いとされている日本の縄文時代や弥生時代の文化度は、実は高かったのではないか、と考え直すようになります。
古代人は横穴式住居や竪穴式住居に住んでいて、縄文時代は狩猟民族、弥生時代は農耕民族と変化して徐々に文化度が高くなって行った、とされている歴史の定説に、どうしても疑問が生じました。
古代人は横穴式住居や竪穴式住居に住んでいて、縄文時代は狩猟民族、弥生時代は農耕民族と変化して徐々に文化度が高くなって行った、とされている歴史の定説に、どうしても疑問が生じました。
古代は科学技術が現代のように発達していなかったのは間違いないのですが、あの壮健な出雲大社は、太古はより巨大な建物として存在していたことが明らかになっています。重機を使わずして、あれだけの建築物を正確に造る技術とは、我々想像している縄文時代や弥生時代の文化度とは全く異なるのです。
2、貝塚は縄文集落で文化が低い証拠?
モースが、1877年に大森で貝塚を発見して以降、各地で同様な貝殻の堆積物が見つかり、縄文時代の集落の跡とされてきました。
これは事実なのでしょうか?
確かに、貝塚が見つかった場所の周辺には古墳があったり、住居跡があったりと、古代に集落があったことは間違いないと思います。
しかし、貝殻の堆積層が見つかったから、縄文時代は狩猟民族で、文化度が低かったと結論付けていいのでしょうか?
これは事実なのでしょうか?
確かに、貝塚が見つかった場所の周辺には古墳があったり、住居跡があったりと、古代に集落があったことは間違いないと思います。
しかし、貝殻の堆積層が見つかったから、縄文時代は狩猟民族で、文化度が低かったと結論付けていいのでしょうか?
3、「考古学」で洗脳
古代(神代終了後の上代)の人達は、かつての神々を崇めるため神社を創建して祀ってきたのです。江戸時代までは、日本神話は普通に歴史の一環として教えられていたはずです。
ところが、そのことを隠したい阿修羅(増上慢偽明治天皇)は、明治維新を機に、すべての常識をひっくり返すために、歴史も変えていったのです。
その洗脳のツールとされたのが考古学という概念です。
4、縄文時代
阿修羅の目的は、神代を縄文時代に改竄することです。そして、上代を弥生時代に。
そのために、化石として残り易い貝殻の堆積層を貝塚と定義し、文化度の低い縄文時代という歴史概念を創りだしたのです。モース以降、考古学という欺瞞の学問によって、皆さんは洗脳されてしまったのです。哀れな事です。